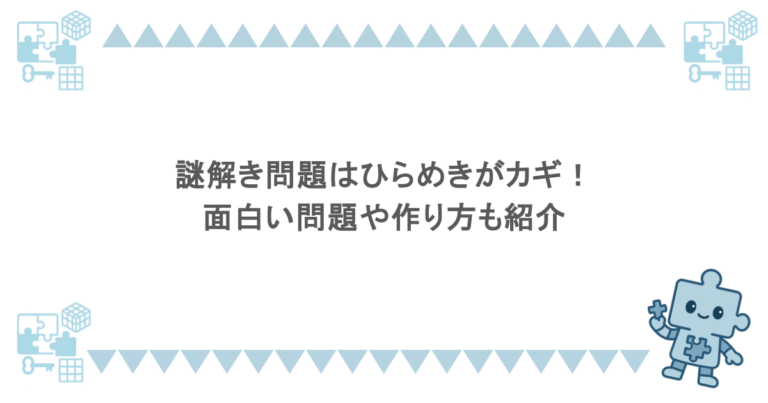突然ですが、あなたは「ひらめき」が得意ですか?
知識ではなく発想の転換で解ける謎解き問題は、定番の知的エンタメ。友達や家族と楽しめる脳トレとして最適です。
この記事では、思わず「なるほど!」と唸る面白い問題や、作り方のコツまでたっぷり紹介します。ひらめきの快感を、ぜひあなたも体験してみてください!
謎解き問題に必要なのは知識ではなく“ひらめき”
「謎解き」と聞くと、難しい知識や複雑な計算が必要だと思いがちですよね。しかし、謎解き問題に求められるのはひらめきであり、実は知識ではなく“発想力”と“視点の切り替え”です。
謎解き問題では、常識や先入観にとらわれず、別の角度から物事を見る力が問われるため、子どもから大人まで誰でも楽しめるのが魅力です。ひとつの問題に対して「どう見るか」が勝負の分かれ目となります。
ちなみに言葉遊びや直感を活かした問題は、古くから世界中のパズル文化の中で親しまれてきました。たとえば、クロスワード 発祥であるアメリカでは、新聞や雑誌で日常的に出題されるなど、言葉と発想を楽しむ文化が根づいています。
ひらめき力を鍛える!おすすめ謎解き問題例
ここからはレベル別に、ひらめきがカギとなる謎解き問題を紹介します。
初級編:シンプルだけどスッキリ!
お子さまや謎解き初心者も楽しめる、言葉遊びや規則性で答えがわかるタイプ問題例です。
A.64
【解説】1×5(いちご)=5、2×4(にし)=8、2×9(にく)=18、はっぱ=8×8=64
A.テントウムシ
【解説】10=テン、10=トウ、6=ム、4=シ
A.テニス
【解説】= を「ニ」と読みます。
A. 保健の先生
【解説】教科は教えないけど“先生”と呼ばれる存在ですね。
中級編:少しひねりが効いた問題
少し考える必要がありますが、発想の転換で解ける「中級のひらめき問題」を紹介します。
A.サンドイッチ
【解説】「と」を「and」に置き換えます。S and 一致→さんどいっち
Q.あか→いき、てき→とく、かさ→きし、ちか→〇〇 〇〇に入る言葉は?
A.つき
【解説】五十音で左側の文字の下の文字が右側の文字になります。
五十音で「ち」の下の文字は「つ」、「か」の下の文字は「き」。よって、答えは「つき」です。
Q.タクシーの中に財布を置き忘れた男性。次の日になって財布を忘れたことに気づいたのに、男性はすぐに財布を取り戻せた。なぜ?
A.彼はタクシーの運転手だったから
【解説】問題文の視点を変えると見えてくる答えです。
Q.駅で電車を待っている人の中に、電車が来ても動かない人がいる。それはなぜ?
A.駅員さんだから
【解説】こちらも視点を変えることで答えが見えてきますね。
上級編:大人も悩むひらめき問題
大人でもじっくり悩む、少しいじわるな謎解き問題を紹介します。
Q.暗い部屋に、ロウソク、ランプ、暖炉があります。マッチで何を最初に灯すべき?
A. マッチ棒
【解説】選択肢はダミー。どれを灯すにしても、まずマッチを灯さないと何も始まりません。
A.伝説
【解説】ほとけ+2=仏に「ニ」を足すと「伝」になり、続けて読むと「伝説」になります。
Q.12+1=稲、4+6=海、10+12=鳥居、3+7=〇 〇に入る言葉は?
A.トラウマ
【解説】数字は十二支の順番、言葉は「十二支の組み合わせ」を漢字に変換して、言葉を作っています。
- 12+1 は「亥(い)」と「子(ね)」→ い+ね → 「稲」
- 4+6 は「卯(う)」+「巳(み)」→ う+み → 「海」
- 10+12 は「酉(とり)」+「亥(い)」→ とり+い → 「鳥居」
よって、3+7 = 「寅(とら)」+「午(うま)」→ とら+うま → トラウマとなります。
Q.掘る→穴、編む→腕、説く→話す、取る→〇〇 〇〇に入る言葉は?
A.高い
【解説】左側の言葉に伸ばし棒「ー」を加えると、英単語ができます。
- 「掘る」は「ホール(hole)」→「穴」
- 「編む」は「 アーム(arm)」→「腕」
- 「説く」 は「 トーク(talk)」→「話す」
よって、「取る」は「トール(tall)」→ 「高い」となります。
自分でも作れる!ひらめき系謎解き問題の作り方
ひらめき系の謎解き問題は、解くだけでなく作ることでさらに面白さが広がります。以下のステップで、簡単にオリジナル問題を作ってみましょう。
1. 答えから逆算する
まずは、問題の答えを先に決めてしまうのがスムーズです。
たとえば「傘」を答えにする場合、「雨」「ぬれない」「頭上にある」など、連想できる特徴を洗い出し、それをヒントに問題文を構成していきます。
逆算することで矛盾のないロジカルな問題を作りやすくなります。
2. 視点のずらしを使う
次に、日常的な状況を一見矛盾しているように見せる演出がポイントです。
たとえば、「雨が降っているのに髪が濡れていない」という状況は、「傘を差している」という情報がなければ常識と反するように思えます。
この視点のずらしが、読者の思考を一度止めさせます。実際は「傘を差しているだけ」という単純な答えでも、視点をうまくずらすことで秀逸な問題に仕上がるのです。
3. 問題文を仕上げる
これまでの要素をもとに問題文を作ります。「雨」「ぬれない」「頭上」など、イメージを喚起するキーワードを厳選して配置しましょう。例題として以下のように仕上げられます。
Q. 大雨の中、男の人は帽子もフードもかぶらずに外を歩いているのに、髪の毛が一切ぬれていません。どうしてでしょう?
A. 傘を差していた
このように、
- 答えから逆算して状況を構成し、
- 視点をずらす工夫を加え、
- 問題文を仕上げる
という3ステップを踏むことで、誰でもひらめき系謎解き問題を作ることができます。
まとめ
謎解き問題の中でも「ひらめき」を要する問題は、知識に依存しない分、誰でも平等に楽しめます。1問1答の短時間で挑戦できるものが多く、SNSでシェアしてみんなで盛り上がることもできるでしょう。
思考力や発想力を自然に伸ばせる“ひらめき系謎解き問題”の出題に、あなたも今日から挑戦してみてはいかがでしょうか?